| 槙尾山桧原越え(槙尾山から三国山) |
桧原越えは西国三十三ヶ所巡りの道
石仏型の町石が残っています。
槇尾山から三国山まで紹介しています。 |
 |
西国三十三ヶ所第四番施福寺です。
この本道の左階段脇に石標が残っています。 |
01 |
 |
この階段を下りずに左にある道を行きます。
石標は
右 ふじ井でら さかい 大坂
左 こかわてら六里 かうやさん七里
 |
02 |
 |
売店横及び愛染堂・弘法大師御剃髪所跡からの道が合流します。
このまま直進。少し下りになります。 |
03 |
 |
この辺下りです。足下を注意してください。
左に一丁石仏があります。少し下るとフラットな道
 |
04 |
 |
三国山・滝畑へは直進です。
右の登りは虚空堂への道です。 |
05 |
 |
先の分岐から10mほど行ったところ
滝畑方面は直進です。右の石段を登ると虚空堂です。 |
06 |
 |
むかしは女人禁制・・・・だったんですね
安永九年は1780年 江戸時代です。
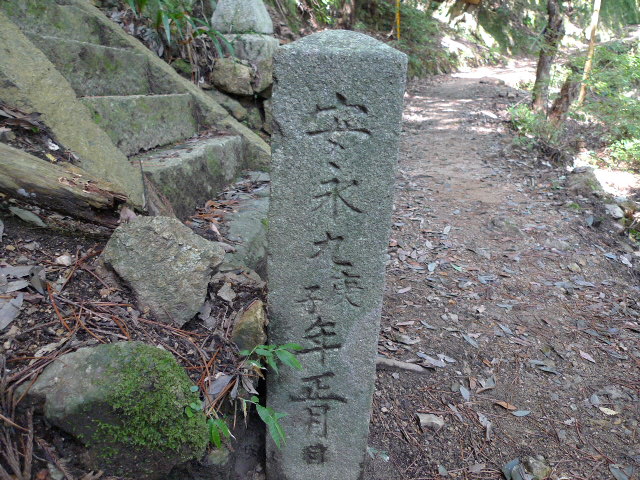 |
07 |
 |
桧原越え・三国山へは右に行きます。ここからしばらく登りです。
左は滝畑方面・ダイヤモンドトレールです。
二丁石仏
  |
08 |
 |
ここからしばらく歩きやすい道になります。
ここを左に少し行くと景色の良い場所があります。
 |
09 |
 |
クリックすると大きな画像が見られます。 |
10 |
 |
ルート上にある木・・・私はかろうじて通れました。 |
11 |
 |
途中道が細くなっていますので注意 |
12 |
 |
桧原越え・三国山方面は直進です。
右は捨身ヶ岳・蔵岩への分岐 |
13 |
 |
桧原越え・三国山方面は直進です。
この先登りになります。
右は捨身ヶ岳・蔵岩への分岐 |
14 |
 |
途中景色の良い場所を通ります。
登りは続きます。 |
15 |
 |
桧原分岐
三国山方面は左です。
右も行けますが五つ辻方面分岐経由になります。 |
16 |
 |
 |
17 |
 |
足下注意
ここから先次の分岐まで歩きやすい道になります。 |
18 |
 |
三国山方面は直進です。
右後ろから先ほど分かれた道が合流してきます。
ここから先登りがきつくなってきます。
 |
19 |
 |
倒木で通れなくなった旧道との分岐
ここから先歩きやすい道になります。 |
20 |
 |
十五丁石仏があります。
石柱には「まきのを」との表示
左から猿子城山からの道が合流してきます。
ここから先少し下って登りになります。
|
21 |
 |
 |
22 |
 |
岩場足下注意、登りです。 |
23 |
 |
三国山方面は直進です。
左に小道 |
24 |
 |
三国山方面は直進です。
左は上山谷方面への小道、下に広い道が通っています。
 |
25 |
 |
三国山方面は直進です。
左から上山谷からの広い道が合流してきます。
槙尾山方面に向かうとき要注意です。
ここから先軽い登り |
26 |
 |
三国山方面は直進です。
右後ろに作業道があります。 |
27 |
 |
三国山方面は直進です。
左から林道が接続してきます。
「まきのを」の石柱が見られます。
 |
28 |
 |
三国山方面は左の道を行きます。
ここから先少し下りになります。
右の広い道は未調査
 |
29 |
 |
二十五丁石仏
 |
30 |
 |
三国山方面は直進です。
ここから先軽い下りです。
右に小道が見られます。 |
31 |
 |
千本杉峠です。
三国山方面は直進です。
右に行くと側川方面です。
 |
32 |
 |
千本杉峠にある三十丁石仏
  |
33 |
 |
少し行ったところにある石標(墓?)
ここから先登りになります。
 |
34 |
 |
途中にある石仏
 |
35 |
 |
途中から舗装路されています。
登りは続きます。 |
36 |
 |
三国山方面は右です。
登りは続きます。
左は作業道? |
37 |
 |
三国山方面は直進です。
右に三国山への小道が見られます。 |
38 |
 |
牛坂です。三国山方面は直進方向(やや右)です。
左は滝畑方面です。
(2010/11/12 (金)指摘により修正)
 |
39 |
 |
三国山方面は右です。
左は作業道ですがフェンスで封鎖されています。 |
40 |
 |
対空送信所
  |
41 |
 |
三国山方面は直進です。
左の道は未調査 |
42 |
 |
右に行くと三国山ですが航空路監視レーダー局舎があります。
四十五丁石仏があります。 |
43 |
 |
 |
44 |
 |
  |
45 |